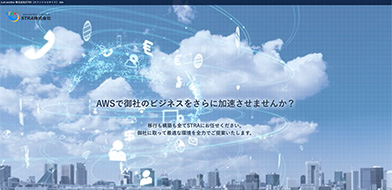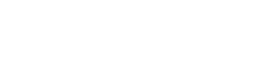ところで、「この、クラウドサービスってなに?」との疑問を投げかけられたら、わかりやすく説明ができるでしょうか?
そもそも、クラウド=雲(cloud)もしくは、クラウド=群集(crowd)となるので直訳すると、「雲を奉仕する」や「群集を奉仕する」といった意味になります。
ITにおけるクラウドはクラウドコンピューティングのことを指します。
このクラウドコンピューティング(以下、クラウド)とは、インターネットなどを経由したサービスの提供と定義できます。
しかし現在では、クラウドという言葉自体が、とても広い意味で使われているので、明確に
何かを定義するのは難しくなっています。
それでは、まずはクラウドについてもう少し掘り下げていきましょう。
AWSを知る前に、クラウドについて知ろう
クラウドは、大きく以下の3つのサービスに分けられます。
SaaS:ソフトウェア【主なサービス例:AWSでのS3 GCPでのGmail】
PaaS:アプリケーション用のプラットフォーム【主なサービス例:AWSでのLambda GCPでのApp Engine】
IaaS(HaaS):インフラ(ハードウェア)【主なサービス例:AWSでのEC2 MicrosoftでのAzure】
※また総称をXaaSとも言いますが、あまり一般的には使われません。
このように、クラウドは目的によって使用すべきサービスが違います。
サービスを決定する前に、目的を明確にして、必要なものを選択していくことが重要であり、最短でたどりつく方法だと言えます。
クラウドは、その配置・環境によっても以下のように分類できます。
パブリッククラウド(共有):個人や企業など不特定多数に向けて提供されるクラウド環境
プライベートクラウド(占有):一つの企業で独自に構築・保有し、使用するクラウド環境(オンプレミス型、ホスティング型がある)
ハイブリッドクラウド:上記を組み合わせ、シーンによってクラウド環境を使い分けること
共有と占有の言葉が示す通り、コストや柔軟性、セキュリティなどで、それぞれ長所と短所があります。使用する環境を考慮してから選択すべきでしょう。
最近では、特に、パブリッククラウドが驚異的な進化を遂げ、オールラウンドに使用できるようになっています。
もはや、プライベートクラウドとの垣根も短所も消えているのかもしれません。
これから比較していくAWSやAzure、GCPはパブリッククラウドに分類されます。
さらに、次世代に先駆け、3サービスを提供するパブリッククラウド事業者は、同時にハイブリッドクラウドにも徐々に力を入れ始めています。
AWS?Azure?GCP?パブリッククラウド事業者のシェア比較
ここまで、クラウドについてみてきました。
ここからは、急激な進化を続けており、今後さらなる利用拡大が期待される、パブリッククラウドを具体的に掘り下げていくことにしましょう。
まず、パブリッククラウド事業者の世界シェア(PaaS・IaaSにおいて)TOP3をみていきます。
1位Amazon【Amazon Web Service】
2位Microsoft【Azure】
3位Google【Google Cloud Platform】
となっています。
日本におけるシェアも、この巨大3事業者で寡占状態となっているのが現状です。
実際に、パブリッククラウドでWEBサービスを構築していく場合、この3事業者のどれを選択するかが自然な流れかと感じます。
それぞれに共通している点として、仮想サーバやOS、ストレージなどのインフラ部分だけではなく、IoT、ブロックチェーン、AI、ビッグデータ活用など、幅広いサービスと最新のトレンドを、全世界規模で提供し続けているところが挙げられます。
細かい仕様や性能、料金は違えど、様々なサービスの組み合わせを、必要な分だけ課金して利用するのが、目まぐるしく変化し続ける現代のITにマッチしていると言えるでしょう。
3大クラウド事業者を比較した結果、AWSが一番である理由
では、どの事業者のどのサービスを利用すべきなのでしょうか?
ここでは、AWSを特にオススメします。その理由をいくつか比較して挙げてみます。
▼AWSは世界シェアTOPを走り続けている
3大事業者のなかで、サービス開始の歴史が一番古く、2006年からサービスを提供している老舗であること。
そして、パブリッククラウドの世界TOPを、現在も牽引し続けているのは事実です。長年培ってきた実績と信頼は、サービスを導入する上でも、顧客へのアピールポイントとしても重要な項目だと言えます。
また、AWSに関連するサービス業者も多く、トラブル時の問題解決や、相談やサポートが受けやすいこと、サービスの最適化に近づけるのが強みです。
▼AWSは対応地域が豊富
パブリッククラウドでは、遅延時間を減らし、障害発生時のリスクヘッジのため。
また、高いセキュリティを担保し、安定したネットワークを提供するために、国や地域ごとに、接続ポイント・データセンターを設置する、ゾーンとリージョンという考え方があります。
もちろん、3大事業者を比較しても、全てが多くの国や地域に対応し、各事業者ともに、対応エリアを随時拡大しています。(※2019年7月時点)
日本国内だけを例にとれば、3大事業者を比較しても大差はありません。
しかし、アジア全体で比較すると、AWSとAzureは中国・韓国・インド・オーストラリアでも、多くのゾーンとリージョンがあるため、やや分があるようです。(※2019年7月時点)
より信頼されるWEBサービスを構築するために、各事業者のエリア詳細を確認しておくと良いでしょう。
各事業者の対応リージョンはこちら
AWS https://aws.amazon.com/jp/about-aws/global-infrastructure/
Azure https://azure.microsoft.com/ja-jp/global-infrastructure/regions/
GCP https://azure.microsoft.com/ja-jp/global-infrastructure/regions/
▼AWSは無料利用枠が多彩で豊富
WEBサービスを構築する際、実際に利用して比較してみたい方も多いでしょう。
AWSでは、無料クレジットは付与されません。(GCP・Azureでは付与されます)
ただし、主要なサービスは最大12ヶ月間まで無料で利用でき、期間が終了しても一定量までは無料で使用できます。(詳細や条件などは変更になる場合があります)
AWSのプランを参考に、どの事業者も価格競争を仕掛けていますが、(2019年7月時点)
これも世界で一番利用されているクラウドだからこそ。
もちろん、個人や企業の好みや使用感があるので、一概には言えませんが、スキルの汎用性や応用を考えていくと、AWSの無料枠からスタートするのが最善策であると考えます。
各事業者の無料枠の確認はこちら
AWS https://aws.amazon.com/jp/free/
Azure https://azure.microsoft.com/ja-jp/free/
GCP https://cloud.google.com/free/?hl=ja
▼AWSはクイックスタートもトレーニングも充実
仮想サーバの初期設定や、アプリケーションソフト開発環境の構築など、これまでは専門知識や幅広いスキルが必須でした。
パブリッククラウド時代では、さまざまなセットアップから専門分野の環境構築、更新され続けるサービスに、併走していくためのカリキュラムが豊富に用意されています。
これに関しても、3大事業者ともにトレーニングプログラムはありますが、わかりやすさと使いやすさ、カリキュラムの質、量でAWSが上回っていると言えます。
各事業者のクイックスタートはこちら
AWS https://aws.amazon.com/jp/getting-started/?nc2=h_ql_le
Azure https://docs.microsoft.com/ja-jp/learn/azure/
GCP https://cloud.google.com/gcp/getting-started/#quick-starts
AWS構築会社の結論とまとめ
総合的に判断しても、AWSの世界シェアが、簡単に変わることは考えにくいです。(5年や10年スパン、単一地域や単月シェアではわかりませんが、まだまだその牙城は揺るがないはず!?)
しかも、パブリッククラウドの歴史は、まだまだ始まったばかりです。
今後の進化と変革に対応すべく、AWSのスキルを磨いていくことは必要になっていくでしょう。
AWSは、世界規模の豊富な顧客と、次を見据えた行動力と加速力で、世界TOPを牽引し続けるでしょう。
この、AWS時代の潮流にいち早く乗り、移行や運用、コンサルティングを手がけ、実績を残し続けてきた当社が、クライアント様の最適なAWSを約束します。