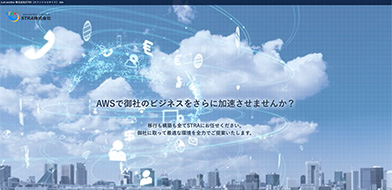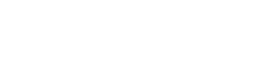クラウドコンピューティングを通じて、インターネット上でさまざまなマシンリソースやアプリケーションを利用することができ、インターネットを通じてできるさまざまなことを実現できます。
月に数万アクセス程度のウェブサイトを構築するだけなら、月額数百円でシステムを運用できます。
オンプレミス環境でシステム構築をすると、負荷に応じてサーバーを増減させたり、システム保持の人的なコストがかかりますが、AWSを利用することで最低限のコストで大きい効果を得ることができます。
AWSを利用することで、幅広い業務領域に対応することができます。
この記事では、AWSで運用できる幅広い業務領域についてまとめます。
幅広いAWSの活用の提案
AWSはAmazon Web Servicesの略で、Amazon.comが運営しているクラウドコンピューティングサービスです。Amazonの社内業務のために立ち上げられたサービスでしたが、2006年に一般に公開され、パートナー制度も手伝って、現在では非常に多くの企業がAWSを使ってシステムを構築しています。
パートナー制度とは、AWSに詳しいシステム関連企業が、他社のAWS導入業務を行うもので、パートナー制度によりAWSを導入した例も数え切れません。
AWSでは一体どんなことができるのか、という疑問や質問を受けることもありますが、AWSではインターネットを通じてできることは、ほぼすべてのことができます。
AWSはマシンリソースやアプリケーションをインターネットを通じて行い、その使用料を支払うというサービスですから、オンプレミス環境でシステムを構築するよりも、柔軟に不可に報じてシステム容量を増減させることができます。
AWSには以下のようなサービスがあります。
・コンピューティング・ネットワーク
・Amazon EC2 :クラウド上の仮想サーバー
・AWS Lambda :サーバーレスコンピューティング
・Elastic Load Balancing :Amazon EC2 用ロードバランサー
・Amazon Route 53 :クラウドDNSサービス
・AWS DirectConnect :既存のオンプレミスとAWSを専用線接続
・Amazon CloudFront :コンテンツ配信ネットワーク
・クラウドストレージ
・Amazon S3 :クラウドストレージ
・Amazon EBS :Amazon EC2 用ブロックストレージ
・Amazon EFS :Amazon EC2 用フルマネージド型ファイルシステム
・Amazon Glacier :アーカイブなどの長期保存向けオブジェクトストレージ
・データベース
・Amazon RDS :フルマネージド型リレーショナルデータベース
・Amazon Aurora :数倍パフォーマンスが向上するMySQL、PostgreSQL 互換リレーショナルデータベース
・Amazon DynamoDB :マネージド型の高速NoSQLデータベース
・Amazon Redshift :ペタバイト規模のデータウェアハウス
・Amazon ElastiCache :フルマネージド型インメモリデータストアとインメモリキ ャッシュ
・監視・メッセージング
・Amazon ClroudWatch :クラウド及びアプリケーションのモニタリング
・Amazon SNS :プッシュ通知サービス
・Amazon SQS :フルマネージド型メッセージキューサービス
・AWS CloudTrial :アカウント利用ログの記録・履歴管理
・IoT・人工知能・機械学習
・Amazon Machine Learning :機械学習テクノロジーサービス
・AWS IoT :デバイス間接続のためのマネージド型プラットフォーム
・Amazon Polly :深層学習を利用して文章を音声に変換
・Amazon Lex :音声認識、テキストの深層学習によりチャットボットなど の対話型インターフェースを実現
・Amazon Rekognition :深層学習に基づく画像認識サービス
・開発者用ツール
・AWS CodePipeline :アプリケーションのアップデートを可能にする継続的デ リバリーサービス
・AWS CodeDeploy :インスタンスへのコードデプロイを自動化
・AWS CodeCommit :プライベートGitリポジトリをホスティング
AWSのクラウド推奨構成例
AWSではインターネットを通じて構築できる多くのシステムを構成することができます。アクセス数が数万程度のウェブサイトであれば、月額数百円で構築できます。
例えば次のような構成が考えられます。
ウェブサーバーとして利用するAWSサービス :Amazon S3
DNS設定を行うためのAWSサービス :Amazon Route53
AWSでは定量性の料金体系を採用していますから、ウェブサイトのPV数によっても月額費用が変わります。
1ページ当たり30個(1ページ当たりの総サイズ3MB)のファイルで構成された、月間10000PVのウェブサイトであれば、6.29USDで構成できます。
・Amazon S3
データ容量料金 $0.100 / GB × 30MB 月額費用$0.100
データ転送料金 $0.201 / GB × 30GB 月額費用$3.60
ダウンロードリクエスト料金 $0.04 / 10000リクエスト×149850リクエスト 月額費用$0.5994
アップロードリクエスト料金 $0.05/1,000リクエスト×10,000ファイル/月 月額費用$0.5
・Amazon Route53
ホストゾーン $0.50/1ホストゾーン/月×1ゾーン 月額費用$0.50
標準的クエリ $0.500/100万クエリ×200万クエリ 月額費用$1.00
ストレージとして利用しているAmazon S3は、3か所以上のロケーションでデータ保管を行っているため、耐久性の高いウェブサイトを構築することができ、低コストで利用できます。
ウェブサイトを運営する上で注意しなければならないのが、アクセス数の増加に伴うサーバーのスペックアップが必要になる場合です。
オンプレミスでウェブサーバーを置いていた場合には、例えばイベントの告知やダウンロードコンテンツの配信をするときに、アクセス数の増加が見込まれる場合には、サーバーにパッチを適用したり、サーバーのスペックアップが必要になります。
その際に、一度サーバーを停止して、データを抽出、代替サーバーへ切り替えて設定をして稼働させる、という作業労力とコストがかかります。
AWSでサーバーの追加を簡単な操作で行うことができますし、IPアドレスの切り替えなどもElastic IPを利用することで短期間で行うことができます。
ウェブサイト・サービス停止を回避するウェブサーバーのクラウド構成例は以下のようになります。
サーバー環境 :Amazon EC2
固定IPアドレス管理 :Elastic IPアドレス
ブロックストレージ :Amazon EBS
DNS管理 :Amazon Route53
Amazon EC2 のメインサーバーがあり、必要に応じてサブサーバーを利用します。
Elastic IPでIPアドレスの管理をし、データの管理はAmazon EBSストレージとAmazon EC2 AMIを通じて行います。
Amazon Route 53 DNS
↓
Amazon EC2 Elastic IP(IPコントロール)
↙ ↘
Amazon EC2 ⇔ Amazon EBS ⇔ Amazon EC2
(メインサーバー) (ストレージ) (サブサーバー)
↘ ↗
Amazon EC2 AMI(イメージファイル)
AWSクラウド推奨構成例2
現在幅広い業務領域で、オンデマンド動画配信によるサービスの紹介や、動画広告を配信しています。このオンデマンド動画配信をオンプレミス環境で行う場合、ピーク時のトラフィックに合わせて、そのトラフィックに耐えうるシステムを構築する必要があります。
データセンターとの契約には、最低契約期間が設定されていることも多く、初期コストと月額費用の継続コストも必要です。
AWSでオンデマンド動画配信をする場合には、初期コストは必要なく、利用した分のみの料金が請求されますので、コストの無駄を省けます。
一か月期間限定のオンデマンド動画配信を想定した場合、以下のような構成になります。
コンテンツ配信ネットワーク(CDN) :Amazon CloudFront
メディア変換 :Amazon Elastic Transcoder
バックアップ用ストレージ :Amazon S3
配信者→<アップロード>→Amazon S3→Amazon Elastic Transcoderで動画変換
→Amazon CloudFrontで動画配信→視聴者
以上の構成で、250MBの動画を60本変換・配信し、合計4000回の動画再生を想定すると以下のような料金になります。
ストレージ関連費用 :$3.34
CDN関連費用 :$143.37
メディア変換関連費用 :$30.60
合計 :$177.31
以上の構成は一例で、他にもさまざまなシステムが考えられます。
恒常的に動画を配信したり、ライブ動画配信などであれば、別の構成も考えられます。
最後までご覧くださってありがとうございました。
この記事では、AWSを幅広い業務領域に適用できること、またその一例として、ウェブサイトをAWSを利用して構築する場合の構成例や、動画配信のための構成例をご紹介しました。
すべての方に最適なシステム構成というのは存在しませんので、詳しくはAWSに問い合わせるのが一番だと思われますが、AWSを通じて幅広い業務領域でさまざまなシステムを構築できること、コスト削減につながる可能性があることなどをご理解下されば幸いです。